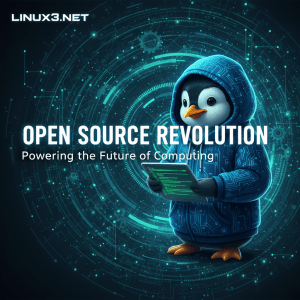AIの脅威から身近な不正アクセスまで!今知るべきサイバーセキュリティ最新動向 2025 🛡️(2025年10月2日ニュース)
中小企業の7割以上がセキュリティ対策に不安を感じる中、証券口座の乗っ取りでは家庭のテレビ受信機が踏み台にされるなど、サイバー攻撃はますます巧妙化・多様化しています。😱 一方で、AIの急速な進化は「AIのためのセキュリティ」という新たな課題を生み出し、企業や政府はその対応に追われています。本記事では、私たちのデジタル資産と情報を守るために今知っておくべき、最新のセキュリティニュースを厳選してお届けします! 🔍
中小企業のセキュリティ対策、7割以上が「不十分」と回答
中小企業のサーバーセキュリティ「7割以上が対策不足」--GMOグローバルサイン・HD調査
GMOグローバルサイン・ホールディングスが行った調査によると、中小企業のサーバー担当者の95.8%がセキュリティ対策を「重要」と認識しているにもかかわらず、実に70.9%が「自社の対策は不十分」と回答していることが明らかになりました。😥 その主な理由として「専門知識の不足」「人員体制の不備」「予算の確保ができない」が挙げられており、多くの中小企業がリソース不足の中でセキュリティリスクと向き合っている厳しい現状が浮き彫りになっています。約4人に3人がセキュリティ面に不安を感じており、継続的に相談できる外部の専門家や伴走支援体制の必要性が高まっています。
証券口座乗っ取りに家庭のSTBが悪用か?見過ごされるIoT機器の脆弱性
証券口座乗っ取りの“STBが踏み台”報道がケーブルテレビ業界に波紋 問題は「ネット通販等で売られている管理されていない端末」
証券口座への不正アクセス事件で、一般家庭に設置されたテレビ用受信機(STB)が攻撃の踏み台として悪用された疑いが報じられ、波紋を広げています。特に問題視されているのは、ケーブルテレビ事業者が管理する端末ではなく、インターネット通販などで販売され、セキュリティ管理が不十分なIoT機器です。これらの機器が攻撃者に乗っ取られ、不正アクセスの温床となる危険性が指摘されています。IPA(情報処理推進機構)は、セキュリティ基準を満たした製品を示す「JC-STAR」ラベル付き製品の使用を推奨しており、身近なIoT機器のセキュリティ対策が急務となっています。🏠
英国政府、再びAppleにバックドア要求!暗号化とプライバシーを巡る攻防続く
Appleのクラウドストレージに対するバックドア作成をイギリス内務省が再び命じていたことが判明
イギリス内務省が、Appleの暗号化されたクラウドストレージに対し、捜査機関がアクセスできる「バックドア」を設けるよう再び要求していたことが判明しました。2025年初頭の同様の要求は強い反発を受けて撤回されましたが、今回は「イギリス国民のユーザーデータ」に限定して再度命令が出された形です。これに対しAppleは、「これまでバックドアを設けたことはないし、今後も設ける予定はない」と一貫して拒否する姿勢を表明。ユーザーのプライバシー保護と国家の安全保障をめぐる対立は、今後も続きそうです。🔒
パスキー普及の壁?知名度は8割でも「よくわからない」が多数
「パスキー」知名度は8割だが理解は限定的 ウェルスナビ調査で浮かぶ課題
パスワードレス認証を実現し、フィッシング詐欺に強いとされる新技術「パスキー」。ウェルスナビの調査によると、その知名度は80.3%に達する一方で、特徴を「理解していて、説明できる」と答えた人はわずか13.0%にとどまりました。多くの人が「名前は知っているが、具体的にどういうものか分からない」状態です。相次ぐ証券口座の乗っ取り被害を受け、セキュリティへの関心は高まっていますが、パスキーのような有効な対策がユーザーに正しく理解され、活用されるまでにはまだ課題があるようです。🔑
「AIのためのセキュリティ」が必須に!AI TRiSMフレームワークとは?
生成AIの活用が急速に進む中、企業は「AIのためのセキュリティ(Security for AI)」という新たな課題に直面しています。これは、AIモデル自体を敵対的攻撃やデータ改ざん、盗用といった脅威から守る考え方です。米Gartnerが提唱する「AI TRiSM(AIの信頼・リスク・セキュリティ管理)」は、この課題に取り組むための包括的なフレームワーク。AI利用時の情報漏洩を防ぐCASBやDLPといった技術的対策と、社内ガイドラインの策定といった組織的対策の両輪で、AIを安全に活用する体制構築が急務となっています。🤖
暴走するAIエージェントを止めろ!Oktaがリスク検出・管理の新機能を発表
Okta、リスクのあるAIエージェントの検出・特定、アクセス管理などを行う新機能を発表
自律的にタスクを実行する「AIエージェント」の利用が広がる一方で、誤設定や管理不足によるセキュリティリスクが懸念されています。この課題に対し、ID管理大手のOktaがAIエージェントのセキュリティを強化する新機能を発表しました。「Okta for AI Agent」は、リスクのあるエージェントを自動で検出し、アクセス制御やガバナンスを強制することで、AIエージェントのライフサイクル全体にわたるセキュリティ確保を支援します。AIが自律的に動く時代に不可欠な管理ソリューションとなりそうです。👮
ブラウザが危ない!不正メモリアクセスを防ぐ新セキュリティツール「Seraphic」
Webブラウザをサイバー攻撃から保護する「Seraphic」、不正なメモリーアクセスを無効化─日立ソリューションズ
日常的に利用するWebブラウザが、巧妙化するサイバー攻撃の標的となっています。日立ソリューションズは、ブラウザの脆弱性を狙った攻撃からデバイスを保護する新ツール「Seraphic」の販売を開始しました。このツールは、ブラウザのJavaScriptエンジン上に保護レイヤーを構築し、不正なメモリーアクセスを無効化することで、従来の拡張機能では防ぎきれなかった高度な攻撃にも対処します。コピー&ペーストやスクリーンショット操作の制限も可能で、企業のデータ保護を強力にサポートします。🛡️
SBI系で暗号資産が不正流出、高まるデジタル資産管理のリスク
SBI系で暗号資産不正流出、DMMビットコイン顧客資産を引き受けたVCトレードに影響なし
SBIホールディングス傘下で暗号資産マイニング事業を手がけるSBI Cryptoにおいて、保有する暗号資産の一部が不正に流出したことが発表されました。同社は業績への影響は軽微としていますが、デジタル資産を狙ったサイバー攻撃のリスクが改めて浮き彫りになった形です。なお、暗号資産交換業を営むSBI VCトレードやビットポイントジャパンは管理主体が異なるため、顧客資産への被害は一切確認されていないとのことです。💸
Wikipediaも戦々恐々…AIがもたらす「有害コンテンツ」と「偏見」のリスク
ウィキメディア財団がAI・MLなどによるリスク評価レポートを公開
ウィキメディア財団が、AIや機械学習(ML)がWikipediaなどのプロジェクトに与える影響についての人権リスク評価レポートを公開しました。レポートでは、AIが有害コンテンツの生成を大規模かつ高速に促進するリスクや、既存の社会的な偏見を増幅・永続化させてしまう可能性を指摘。特に、特定の個人やコミュニティを狙った誹謗中傷が自動生成される危険性に警鐘を鳴らしており、AI時代の情報プラットフォームの健全性をどう保つかが大きな課題となっています。🌐
なぜアプリは簡単に入らない?AppleとGoogleの「見えない壁」とセキュリティ
「Appleはサードパーティアプリのインストールフローを複雑にすることでインストールしにくくしていた、Googleは依然として改善されていない」とEpic Gamesが指摘
Epic Gamesが、Appleはサードパーティ製アプリのインストール手順を意図的に複雑にし、ユーザーを離脱させることでApp Storeの優位性を保っていたと指摘しました。実際に、EUのデジタル市場法を受けてiOS 18.6で手順が簡略化されると、離脱率は65%から25%に激減。このデータは、プラットフォーマーの設計思想がユーザー行動に与える影響の大きさを示しています。Epic Gamesは、Androidにおけるインストールプロセスも依然として複雑であり、OSのセキュリティ設計と公正な市場競争のバランスが問われています。📲
考察
今回のニュースを俯瞰すると、セキュリティの脅威が「AIという新たなフロンティア」と「身近な機器の脆弱性」という両極で急速に拡大していることがわかります。
AI分野では、単にAIを悪用した攻撃だけでなく、「AIそのもののセキュリティ(Security for AI)」や自律的に動く「AIエージェントの管理」といった、これまでになかった概念が現実的な課題となっています。企業はAI導入による生産性向上を期待する一方で、その信頼性やガバナンス、プライバシーリスクへの対応に迫られています。これは、技術的な対策だけでなく、AI TRiSMのようなフレームワークに基づいた組織的な取り組みが不可欠であることを示唆しています。
一方で、家庭にあるSTBが不正アクセスの踏み台になるなど、IoT機器のセキュリティ対策の甘さが改めて浮き彫りになりました。また、パスキーのような強力な認証手段が登場しても、ユーザーの理解が進まなければ宝の持ち腐れとなってしまいます。
国家レベルでは、政府が暗号化解除のためにバックドアを要求する動きもあり、個人のプライバシーと国家安全保障の対立は今後も避けて通れないテーマであり続けるでしょう。
これらの動向から、これからのセキュリティ対策は、最先端のAI技術を理解すると同時に、足元のデバイス管理や従業員・ユーザーへの啓蒙活動といった、地道な基本動作の徹底がますます重要になると言えます。技術と人間の両輪で、巧妙化する脅威に立ち向かう姿勢がこれまで以上に求められています。
#サイバーセキュリティ
#情報セキュリティ
#AIリスク
#不正アクセス
#脆弱性